ニューヨークに暮らし、アディダスやAXE、グーグルなどの世界的広告キャンペーンを手がけるCDでありつつ、E テレで分かりやすく楽しく映像技法を紹介してくれる番組の制作者でもある。コンテンツに向き合う時は「つくり方からつくる」。で、日本に映像作家を増やし、未来のテレビ視聴者をも生産中。ジャンルを問わないマルチなつくり手に、そもそもの「つくり方」を聞いてみた。
※本記事は2015年9月発売のSynapseに掲載されたものです。
PARTY
川村真司
東京生まれ、サンフランシスコ育ち、ニューヨーク在住。慶応義塾大学佐藤雅彦研究室で「ピタゴラスイッチ」などの制作に携わる。卒業後CM プランナーとして博報堂に入社。BBH Japan の立ち上げに参加し、アムステルダムの180、ニューヨークのワイデン&ケネディなどでCDを務めたあと、PARTY を共同設立。名だたるブランドのグローバルキャンペーンを手がけつつ、ブックデザイン、ミュージックビデオのディレクションに、テレビ番組の制作も。2012 年からスタートした『テクネ 映像の教室』はこの8 月にシーズン4を放送、次回は12月放送予定。
コンテンツは、「つくり方からつくる」。
ミュージックビデオから広告系動画コンテンツ、プロダクトまで。様々な表現の分野でつくる。そのおおもとにあるもの。
― 川村さんの映像の原体験ってなんですか?
「『スター・ウォーズ』を最初に見た時ですね。物語も面白かったけど、デス・スターとかをミニチュアで撮って合成してるのがすごくて、“悔しい”と思ったんです。別に映像なんて撮ったことのない子どもが。今も映像に“面白いですね”は言うけど、なかなか“悔しい”までは言わない。つくり手からしたら、“悔しい”は、最上の褒め言葉なんです。今考えると、つくり方への興味は当時からあったのかもしれません」
― 実際に映像に関わるのは大学での佐藤雅彦研究室ですね。
「授業で発表する課題ではなく、実際に社会に提案するものをつくるという方針の研究室でした。例えばNHKと話がついていて“こんな枠があるからみんなで企画を考えてみよう”と。佐藤先生が特殊なのは“自分なりのルール”をつくれること。デザインの前の枠組みから考えるんです。研究室でも、デザインの仕方は教えてくれない(笑)。
“考え方から考える”べきと。それを僕なりに解釈した結果たどり着いたのが、“何かを制作する時は、つくり方からつくる”ということ。毎回全然違うものをつくってるように見えると思うのですが、共通点はそこです。ストーリーがかわいいとか、絵がかっこいいのは、二次的な面白さ。
人がこれまで気付かなかった心のスイッチを入れるような表現は、根源的な面白さって何かを問わないとダメだと。逆にそういうアイディアなら、打席に立った時点で三塁打ぐらいは確定している。あとは表現次第でホームランや場外ホームランになるっていう」
― つくり方を考える、とは?
「例えばミュージックビデオをつくる時、パッと思いつくのは機材とスタジオを借りて役者を雇ってバンドを撮るという手順。でも一回それを取っ払う。ウェブカムだけでつくってみようとか、カメラのストロボの光を制御してピクセルのアニメーションをつくれるかな、とか。
みんなと同じつくり方をして同じ土俵で戦うのではなく、土俵を違うものにしちゃう感覚。その方が誰も見たことがない表現にたどり着きやすいと信じてます。その時気を付けているのは、つくり方が上滑りしてはいけないということ。自分がどんな技法を使いたいかではなく、そのコンテンツが伝えるべきメッセージをベストに伝えるのが最も重要なので。
ミュージックビデオの場合は、曲を聞き込み、歌詞をすごく読んで“こういうことですね?”とアーティストに聞いたうえでベストなつくり方をしているつもりです」
― 川村さんはCGはあまり使わない印象がありますが。
「見る人にどうやったら共感してもらえるかをすごく考えていて。微妙な揺らぎとか、人の手から生まれる不完全さみたいなものに人は共感覚を持ちやすいと信じているんです。それをCGでつくるのはすごく難しい。
映像がYouTubeにアップされると、CMでもMVでも番組でも、何億回再生とかされてるスマホで撮ったワンちゃんの動画と比べられたりします。そのようにコンテンツのジャンルや垣根がなくなっている今、何で競うかというと、そんな共感をいかにあの手この手で生むかということだと思っています」
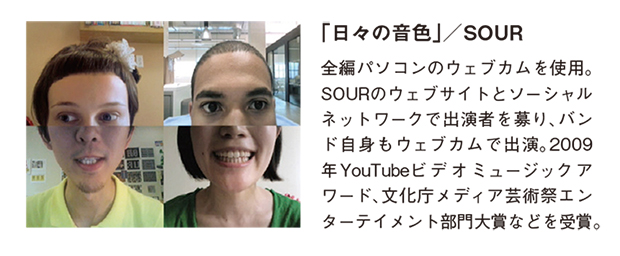

『テクネ 映像の教室』のつくり方。
2012年からスタートした映像技法を解説しつつ、楽しい動画を見られる番組。この番組を始めたのが川村さん。なぜ? 目論むところは?
―『テクネ』はどういう経緯で始めたんですか?
「Eテレの『日曜美術館』プロデューサーの倉森京子さんが、SOURのビデオを見て、一緒に番組つくりませんかと連絡をくださったんです。最初に今とは違う『オンラインのおもしろ動画を集めて見せる番組』という企画書を見せられて、思わず“そのままだとつくる意味がないです”って言っちゃって。新しい企画を考えるから1日だけ時間をください、と」
― OKだったんですか?
「はい。その懐の深さと実現力が倉森さんのすごいところです。それで動画をただ見せるんじゃなくて、何がしかの系統で分類すれば、そこにきっと新しい気付きがあると思ったんです。毎回ひとつの映像技法を紹介して、それをベースにした古典的な映像から最新のものまで、プロ・アマ問わず紹介したら、当初の“おもしろ動画を見せる”を成立させながら、映像技法の力や映像制作の魅力も伝えられる。これを見て映像を志す人が増える番組にできたらいいなと、企画書にして渡したら、“面白い! 通してきます!”って(笑)」
― 普段から映像を分類されたりしてるんですか?
「全然。仕事柄&趣味でたくさん映像は見ているので、日常、僕が見て面白かった動画を『テクネ』のミーティングに合わせて分類し直す感じです。テクネチームでグーグルドキュメントにリストをつくって、それを埋めていくんです。同じくプロデューサーの岡本美津子さんはアニメーションのプロなので、僕も知らなかった50年代のアニメーションをセレクトしてこられたり。自分のアーカイブの整理になりつつ、知らない映像も見られてすごく楽しいですね」
―いいですねー。
「ええ。裏テーマは“自分が楽しめる番組”ですから(笑)。『テクネ・トライ』という、クリエイターの方に課題を与えて映像をつくってもらうコーナーも、僕がお近づきになりたい人や、新作を見てみたい人にオファーしたりして」
― 引き出しも増えますね。
「語弊があるかもしれませんが、それはないですね。むしろ自分の引き出しの整理というか……。個人的に、他の作品を見るのはどちらかというと、そういった作品に似たものをつくらないようにするためという側面が強いんです。素人や映像作家を目指す人にとっては、“こんなに簡単なんだ”“こうすればできるかも”って知っていただき、すでにつくっている人たちには“あ、これもやられた”“しかもこんなにすごいレベルで!”って、悩んでもらうのがテーマです(笑)。
番組は今5シーズン目に入っていて、映像作家とそのコミュニティを広げるためにいろいろと構成を進化させてきました。視聴者に実際に映像づくりに着手してもらえるようコーナーを追加したり。それがいちばん顕著なのが“テクネID”の一般公募。つくり始めたみんなのための出口が欲しかったんです。
この春に『IDアワード』という、テクネIDだけの番組をつくったら、なんと900件ぐらい応募があったんです。プロだけでなく、一般にもこんなに映像をつくる人が増えたのを見ると、始めて良かったなと感じます」

テレビの未来の視聴者をつくる。
『テクネ』のみならず、新しい試みも始まっている。それは子どもたちにテレビの使い方をレクチャーする番組! ? 川村さんの見るテレビの行く末とは。
―「前のあの作品みたいにつくってください」っていうオファーはないんですか?
「ありますね。でも僕のあまのじゃくが首をもたげて拒否してしまう(笑)。とりあえず1回持ち帰らせてもらって、伝えたいメッセージや、やりたいことを聞いて、考えて、違う案の方がよさそうだったらそれを提案させてくださいと。で、だいたいの場合、違う案の方がいいんですよ」
― 川村さんが、自ら表現したいことってないんですか?
「実はほとんどないんです。あるのはむしろ、“こういう表現方法やこういう見せ方をしたことがないからやってみたいな”っていう実験的興味ですね。“まだ誰も手を付けてない考え方見つけた!”っていう時が、いちばん興奮します。ただ、映像はひとりではなかなか撮れないし労力もかかるので、まずはジャンルなどにこだわらずにやってみています。昔、虹が出るパラパラマンガつくったのもそんな実験のひとつでした」
―これまで4シーズン『テクネ』を続けてこられて、テレビで実験してみたいことは出てきましたか?
「テレビのコンテンツをつくったり、テレビというメディアへの知識が増えると、やっぱり実験したくなりますね。今、倉森さんと一緒に『かおテレビ』というインタラクティブ番組をつくっています。パイロットを今年の初めにつくって、好評だったので追加で4本。視聴者がスマホでつくった顔がテレビに飛び込んで歌う番組です」
―なぜそんな企画をやろうと思ったんですか?
「ハイブリッドキャストっていう、インタラクティブ放送の仕組みがあって。今まではスポーツのテロップやニュース速報程度にしか使われていなかったのですが、それをもっとダイナミックに活用できないか。今後こういった新しいテレビとの関わり方をしていくのは子どもたちなので、インタラクティブ放送の楽しさを覚えてもらえるようなものがないとテレビの先がないんじゃないかって思ったんです」
―テレビの未来を考られたってことですよね。今後テレビはどんな風になっていくと思われますか?
「いずれテレビ的なものはパソコンとひとつになっていくような気がしてるんですけど、とりあえず居間のど真ん中にはあの黒くて四角い箱がドーンと置かれてるわけでしょ? 水道とかに近い状態でインフラ化しているデバイスって実はほとんどない。映像をつくる者としてそれを使わない手はない。
ただコンテンツ的には他のデバイスとの時間の奪い合いになりますよね。YouTubeで動画を見てる方が面白いということになれば、そっちにいっちゃうから、コンテンツ力を鍛えていかないと厳しいでしょう。メディアとしては成熟しすぎちゃって、番組をつくるやり方が限界にきてる面もあると思うので、Eテレのように、僕みたいな完全に外部をつくり手として入れてみるのは面白いと思いますよ。
ただEテレは最近それがおいしいと気付いて、ちょっとやりすぎている気もしますが(笑)、でも新しい血を入れることで新しいアイディアが生まれるのは間違いないことだと思っています」






