【テレビのミライを創る】 世代と世代をつなぎながらテレビ&広告のミライを創る フジテレビ 黒木 彰一さん×電通 北風 祐子さん
(左から)フジテレビ 黒木 彰一氏 電通 北風 祐子氏
テレビ放送が始まって約70年。その裏には多くの人たちのアイデアや挑戦、それらの化学反応があり、テレビはここまで発展してきました。
Synapseでは、そのテレビの発展を今後も継続的に生み出し続けるために、テレビのプロデューサーやディレクター、広告のクリエイターやプランナー、そしてビジネスプロデューサーなど多種多様な方々が語り合う企画を立ち上げることにいたしました。それぞれの視点とアイデアがぶつかりあい、「テレビの世界でこれから仕掛けられそうな新しいコト」をいっしょに考える新企画【テレビのミライを創る】、スタートです!
第一回目は、フジテレビの敏腕プロデューサーとして名高い黒木さんと、電通でチーフ・ソリューション・ディレクターを務める北風さん。異なるようで近しいフィールドで活躍するお2人の対談では、同世代ならではの鋭い視点や葛藤も浮き彫りに!テレビや広告のミライは、"狭間の世代"にかかっているのかも...。お2人の日々の奮闘の様子や熱い想いが溢れる対談をお送りします。
"年齢の壁"をどう捉えるか
黒木
僕が1969年生まれで、北風さんが1970年2月生まれだから、同学年ですよね。北風さんは小学生の頃からタモリさんを尊敬されているとか?! 僕も『笑っていいとも!』を担当していたので、何かご縁を感じます。子どもの年齢も近いんですよね。うちは娘が24歳で息子が22歳なんです。本日はよろしくお願いいたします。
北風
そう!同じ学年、うれしいです(笑)。タモリさんファン歴は40年になります。子どもは娘が20歳で息子が16歳なので、確かに似ていますね。こちらこそよろしくお願いいたします。
たくさん伺いたいことがあるのですが、最初に「年齢の区切り」に対する黒木さんのお考えを聞かせてください。テレビも広告も「生活者と向き合う」という点では共通していて、年齢で区切ってターゲティングをするケースが多いのですが、最近私はそこに懐疑的になっていて。
たとえば、インフォマーシャルは50代以上の方々が主なターゲットになっていますが、30代の方でもインフォマを見て物を買うことはありますよね。なので、20代や30代、もっと若い10代向けのインフォマみたいなものが、世の中にあってもいいんじゃないかと思っているんです。人が物を欲しくなるときのスイッチって、若い方も年配の方も、あまり変わらない気がします。それと同じように、人がおもしろいと思うことや笑えることにも、もしかしたら年齢の壁はないのかも...と思っているのですが、黒木さんいかが思われますか?
黒木
北風さんのおっしゃるとおり、見ておもしろいと思ったり、惹かれたり、興味を持ったりする事柄は、年齢差がなくなってきている感じがします。例えば番組の構成会議でも、「3層(50歳以上)には、この情報が好まれる」なんていう話を、若いディレクターたちほど、あまりしなくなってきている気もします。でも、一方でまだまだ根強く「年齢層のイメージ」もあります。
北風
自宅で家族4人でテレビを観ていても、同じところ、同じエピソードでみんなお腹を抱えて笑ったりしますからね。結局、おもしろいと感じることやワクワクすることは、根っこはみんな一緒だと思うので、人を年齢で区切るのはやめたほうがいいんじゃないかなって。F1層(20~34歳女性)とF2層(35~49歳女性)の区分も、35歳になった途端に変わるという考え方はちょっとおかしい。人は歳の区切りで生きているわけではないのに、42歳の誕生日を過ぎてから「42歳のあなたへ」というネット広告がたくさん来るようになったときも、すごく違和感がありました。
黒木さんの手がけてこられた番組って、あまり視聴者の年齢を問わないものが多いですよね?
黒木
長いスパンで同じ番組に携われてきたのは本当にラッキーだったと思います。「番組が視聴者の皆さんと一緒に成長してゆくことができる」という感覚で制作することができたんですよね。「みなさんの人生の中に番組が存在できる」というか。そうなってくるとターゲットとか年齢層とかはあまり関係なくなってきて、2世代3世代に渡って番組を見てもらえたり、自分の "日常の中の大事なもの"として認識してもらえたりする。『SMAP×SMAP』や『笑っていいとも!』を作っていて、そう見てもらえることを願っていましたし、また、信じていたのもそういう部分でした。

n=1の価値
北風
黒木さんはテレビの世界でおもしろい方やおもしろいことをたくさん見てきたと思うのですが、あたりまえのように"そこにタモリさんがいる"という人生を歩んでこられたなかで、今はどんなことを「おもしろい」と感じていますか?
黒木
「あたりまえのようにタモリさんがいる人生」(笑)! その言葉が非常におもしろいです。まさにそれこそずっと『いいとも!』を見てきてもらったみなさまの人生!かも。すみません、脱線しました(笑)。
さっきの年齢の話でいうと、ターゲットを年齢層に置くのではなくて、より具体的で個人的な誰かに見せたい、と思うことが大事なんじゃないかと思い始めています。何を作るときでもまず「だいじなひと目線」というか。
ピチカート・ファイヴの小西康陽さんにお願いして『慎吾ママのおはロック』を作ってもらったとき、家に帰ったら子どもたちが踊りくるっていたのがすごくうれしくて。いまでも忘れられません(笑)。「ある年代をターゲットにして作る」というよりも、「家族に見せたい」、「両親に見せたい」、「彼氏に見せたい」とか、誰かに見せたい感覚が、実は一番大事なのかなと思ってます。
北風
私も「自分が欲しいかどうか」、「子どもにあげて喜ぶかどうか」という視点から考え始めるので、よくわかります。マーケティングの世界では、よく「n=1でモノを語るな」といわれます。nというのは母集団から抜き取った標本の数を表す数字で、世論調査だとn=3000くらいが必要とされています。「n=1でモノを語るな」とは、要は「たった一人の意見でモノを語ってはいけない」という意味なんですが、私はその"1"で十分だと思っているんですよね。3000人の平均値よりも、一人の生々しい声から得られる示唆のほうが多いです。
黒木
広告や商品開発など、生活に密着したお仕事をされている北風さんの視点から見て、"生活者をひきつける"ためのコツみたいなものはあるのですか?
北風
番組と同じ動画ジャンルの広告を例にとると、私の息子の世代は「デジタルネイティブ」と呼ばれていて、スマホと共に生まれて育ってきた人たちです。そうすると、広告は最初の5秒の間に印象に残る何かが起きないとダメなんです。息子に「15秒とか見続けるのはちょっと無理」と言われたことがあって(苦笑)。5秒くらいのところで飽きるんですって。確かに、彼の好きなCMでは、全部、頭の5秒以内に何か事件が起きているんです。おもしろいと感じること自体に世代の壁はないけど、もし若者に買ってほしいなら、早く見せる、山を何個か作るなど、若者ならではのアジャストは必要だと思います。

全員が盛り上がって生まれるモノ
北風
逆に黒木さんご自身はどういう番組にひかれますか?
黒木
番組の出演者の皆さんはもちろん、スタッフやマネージャーさんまで含めて盛り上がっている番組は、魅力的で強いです。「流行ってて活気のあるお店」のイメージです。逆に、キャストやスタッフとのストーリーが持てない番組は、視聴者とのストーリーも持ちづらくて。
北風さんがやっていらしたプロジェクトも、たくさんスタッフの方がいる、ある種の"集団芸"ですよね。テレビも同じで結構人数が多いです。どんな企画だったら面白いのかはそのチームのメンバーの反応でわかるので、そこは大事に考えています。もちろんスターが1人で引っ張っていく番組も素晴らしいですが、ディレクターが何人かいて、みんなでやっている感じになると、うまく回っていきますね。
このことはいわゆる「内輪ノリになること」とはちょっと違うことで。「内輪ノリ」というのはひとつの手法でしかないんです。いまはあまり好まれなくなっている手法ですが。もちろん、僕自身は80年代に『オレたちひょうきん族』でスタッフが画面に出ちゃうようなノリが当時は強烈にカッコ良かったし、もしかしたら僕自身もフジテレビもそういう時代を忘れられないのかもしれないです。それはそれとして。「チームのノリの出し方」は時代によって当然かわりますし、今は今の手法があります。若手の制作者たちはこれから自分たちがどうやってゆくのか当然、考えています。実はこれは楽しみにしているところでもあります。
北風
でも、「中で盛り上がっていないのに外をどうやって盛り上げるの?」というのは絶対にあると思います。クリエイティブでも同じなんです。どのプロジェクトでもスターは1人くらい必要ですが、コピーを考えてくれるスターが必要なときもあれば、全体の仕組みを考えてくれるスターが必要な場合もあって、ケースバイケースです。いつも特定のスターを置くのではなく、その時々に必要なスターを見つけてきて、一緒にやって欲しいとお願いするのが私の仕事の醍醐味ですね。
黒木
なるほど、よくわかります。
北風
いまどきの広告プランニングというと、「全領域ができるスーパースターになれ」と求められがちですが、それは無理です。自分に欠けているものをよく理解して、それがわかっているからこそ、自分にできないところを誰かにお願いして気持ちよくやってもらえるよう、私も自分自身の領域を全力でがんばっています。そうやってチームができていくと、みんなで「いくぞ!」となるのがすごく楽しくて、それがおもしろくてずっとこの仕事を続けている感じですね。なので、スターはいるけどスタッフやメンバーが全員で盛り上がって、家族のような雰囲気で一体となったときに初めてモノを創れるところが、黒木さんの番組作りと似ているなと思いました。
だから、チームの中でうまくいっていない人やおもしろくなさそうにしている人がいないように気をつけています。ケンカしてもいいから、黙っているよりは、みんな言いたいことを言え!と伝えていますね。そのほうが、企画がどんどん良くなっていくんですよ。

"狭間の世代"の葛藤
黒木
"民放連 五輪特別プロジェクトチーム"という僕も含めて民放5局のバラエティの制作者を中心に集まって、電通の澤本さんもご一緒しながら民放連でオリンピックを盛り上げるために『一緒にやろう2020』というプロジェクトを展開しています。ここでも実は「チームのノリ」が非常に大事で、出来ないことも含めて面白く話し合う「ノリ」がないと、チームの外の方々、もっと大勢の方々とも絶対に繋がれない。この場に参加しているみんながその辺すごく自覚的で、民放の文化祭委員をやっているような感じで盛り上がっています。このプロジェクトチーム発案の「思わず捨てたくなるゴミ箱選手権」も開催中ですので、是非ともご注目してもらいたいです!
ただ一方で、若手世代の作り手や広告プランナーは、作り手になっちゃうとジレンマが働いてしまうのではないかという心配もありますよね。というのも、ウェブを中心にデータだとかマーケティング要素だとか、昔より断然精度もあがっていて「いかに効率よくスピーディに」ということが格段に重要になってきている。そんな中で自分が実際に作り手になったときに「何がおもしろいのかな」とか「決まった正解があるはず」と悩んだりしてしまいがちなのでは、と思っています。
そしてまた上の年代の人たちの「効率なんて知らねーよ」的な仕事の仕方に萎縮したりすることがあるかもしれないなと......。これは僕のことですけど(笑)。
この、下の世代をモチベートする方法について、同学年の北風さんには是非ともお聞きしたいです!
北風
背中を見せるしかないと思います。みんないなくなっても最後まで私はやり抜くつもりだから「あなたもついて来なさい」くらいの気持ちで。インターフェイスは優しく丁寧に柔らかく接していますけど、心のなかはある意味では容赦ないというか。お客さんじゃないんだから、つまらないとか言っている場合じゃなくて、自分でおもしろおかしくさせなきゃダメでしょう?って。そういう意味では、私は一人でおもしろがって死んでいって、もう化石になる覚悟です(笑)。
黒木
すごい。
北風
だから、20代の子たちも大歓迎。気が引けちゃうなら、得意な部分だけでもやってみて欲しいですね。ゴールに向けて全能で歩く必要はないという主義なので、パーツで何かを出してくれればそれだけで十分すばらしい。私は自分自身もパーツだと思っていて、みんなのパーツが噛み合ったときに化学反応が起こるのを何回も経験しています。それを若い世代の人たちにも味わって欲しいから、「パーツでいいからとにかくおいで!」という言い方をしています。
黒木
非常に共感します。糸井重里さんもひょうきん族も80年代のスター達は最初の先生だったし、デジタルネイティブの20代は部下だし、ぼくらはちょうど"挟間の世代"なんですよね。僕らは「勝手にやれ」「見て盗め」と言われてやってきましたけど、下の世代は突き放すだけじゃダメですし。
北風
そうですね。だから私は、若い世代が私の知らないことをたくさん知っているということに対して、素直に尊敬しています。それらを0から勉強してやるくらいだったら、尊敬できる彼ら世代に入ってもらったほうが100倍早いので、「一緒にやろうよ!」という感じです。
黒木
しんどいけど、逆におもしろいですよね。みんながみんな同じ考え方ではないし、どこかで断層は必ずあるんですけど、若い人たちはちゃんとしているし遠慮がちだけど、一方で承認欲求も高かったりして。じつは"狭間の世代"のぼくらを、うまく使ってもらっている感じもしますよね。
北風
自分のなかでは"ゆきずりの上司"という言葉を当てはめています。言ってしまえば、人生そのものがゆきずりというか、ほんの一瞬一緒にいられるだけで、当然仕事の中で出会う人たちも、もしかしたら家族ですらゆきずりなのかもしれない。だったら相手に遠慮しないで、自分の思うように絡んでいきたいなって。寂しい思いをすることもあると思うし、それじゃダメだって言われるかもしれないけど、それを怖がらずに絡んでいくと、破片でも噛み合うところがあるんですよね。それが何よりおもしろいなと思うから、あきらめたり、遠慮したりするのはもったいないと感じていますし、若い人たちにもそう考えて仕事に邁進して欲しいです。

「何がおきるかわからない」を追い求める
黒木
北風さんが20代・30代の若手に対して「優れているな」と思うのは、具体的にどんなところですか?
北風
とにかく理解が早くて賢い。会社に長くいるつもりがない人も多いせいか、短い間にできるだけ多くのことを学びたいという意欲がありますよね。あとは、優しくて寛大。自分が若いときなんかより、よっぽど適応力があると思います。いまの時代において、当然のように必要とされているデータ分析能力を発揮できるところも強い。そのようないいところがたくさんある半面、失敗に弱いところはあるかもしれません。
黒木
僕も、失敗に弱いし、あきらめが早いというのは感じています。だから「無駄なことやダメなことをたくさんやってもいいんだよ」っていうメッセージを全身から発信するように(笑)心がけています。彼らが感じる「効率が悪い」考えに、どれくらい付き合ってもらえるか。たとえば、あるタレントさんを番組にキャスティングしたいときに、企画書をメールで送ってマネージャーさんと電話してダメだったらもうそれであきらめる、というのではなくて、そこから作戦をたて始める、ということなんです。
北風
それをやってもダメかもしれないという結果まで想像して、やる前に「無駄だ」と判断しまうんでしょうね。
黒木
ええ。うちのヒットメーカーで、木月という優秀なディレクターがいます。その木月から「サブカルチャーの番組が減っているからやりたい」という相談があって、久保ミツロウ先生を是非キャスティングしようという話になりました。久保先生はテレビには出ないと言っていたけど、久保先生のオールナイトニッポンに木月がケーキを持って毎週通った結果、キャスティングが実現したんです。それが『久保みねヒャダこじらせナイト』の始まりです。
そういうことがあるから、失敗してもいいから、バカなことでもやってみることも必要なんだなって。そういうストーリーって、チームで共有できる昔話みたいな財産になるんですよ。だから、無駄かもと思う球をたくさん投げれば時には当たることもあるので、まぁ本当に当たらないムダな球ばかりたくさん投げてきた気もしますが(笑)。一生懸命伝えていかなきゃなって思っています。
北風
若い世代は、頭がいいだけに結果を先読みして、「これは無駄かもしれない」「やめておこう」という発想に行ってしまいがち。でも、会社を7~8年で辞めると決めているあたりも、何が起きるかわからないという偶然のおもしろさみたいなものを、最初から捨てているのではと感じます。だから若いメンバーには、「一見つまらなそうに見えるけど、やったら実はおもしろい」といった仕事をわざとアサインしたりしています。

満足や幸せは効率化できない
北風
口コミで"人の判断"に関する情報が入りやすくなったことによって、「自分が試してみよう」よりも「誰かに話を聞いてみよう」という雰囲気になっていると感じませんか?たとえば映画の感想をSNSにあげるにしても、誰かの感想を見てから書く人が多いそうで。自信がないというか、「みんなが言っていることをチェックしてから、自分もそれと似たようなことを言っておこう」というような。
黒木
自分で試すのが効率悪く思えるのか、あるいは既に集められるかぎりの情報を元に判断するのがあたりまえだと思っているのかも......。以前もそうだったとは思いますが、その傾向はとっても強くなってきていますね。
北風
先が見えなくて怖いけど冒険してみるとか、やってみたら何かおもしろいことがあるかもしれないって、テレビ番組ならではの魅力ですよね。黒木さんが手がけてこられた番組にもあったような「相手が何を言うかわからない」というおもしろさをふだんから楽しんでいけると、いい企画が生まれるんでしょうね。
いま社内でがんサバイバーのためのカフェ(LAVENDER CAFE)を開催しているのですが、皆さんに企画を募ったら、吉本新喜劇に行きたいとか、はとバスツアーに乗ってみたいといった案が出ました。「行った先で何があるかわからない。おもしろくないかもしれないけど、おもしろいかもしれないから、ひとまず行ってみよう」といったノリで参加できたらいいですよね。
今のテレビ番組に関しても、最初からサッカー好きはサッカー、ドラマ好きはドラマ、バラエティ好きはバラエティを観てくださいと決まっているチケット制のように感じてしまうんですけど、本来のテレビって、「全然関係ない人が来ちゃってもめちゃくちゃおもしろかった」というようなことが起こせる可能性を秘めていると思うんですよ。
黒木
そうですよね。幸せとか満足は個々人のものだから、ホントは効率化できないですよね。計測化もしにくい。
レギュラーのバラエティー番組がおもしろくなってゆくには、もちろん企画やゲストが良いことも大事なんですが、ちょっと地味めかなぁと思っていた放送回が反応が良かったっていうことが不思議とあるんです。そういう回を後から振り返ると、出演者が一生懸命になっている様が出ていたり、制作陣の効率を重視しない遠回りが逆に功を奏していたりします。"汗の量"が伝わっていたというか。ゲストと企画とパッケージだけでは番組は作れないんだなと最近感じます。共感してもらうためには、やはり汗や思いの量が必要かと。あー、また昭和のバラエティー観出しちゃいました(笑)。
北風
制作陣が裏でかいた汗の量は、画面を通じてわかるものなんですか?
黒木
チームのかいた汗の量は確実に出ます。そして、それが演者さんの表情とか立ち振る舞いにすごく自然と出ている番組は信用してもらえるのだと思う。われわれは生き物だから、やっぱりイキイキしている魅力的な生き物が見たいのだと思います。もちろん、カラダの汗だけでなく、アタマの汗、ココロの汗も含めて。
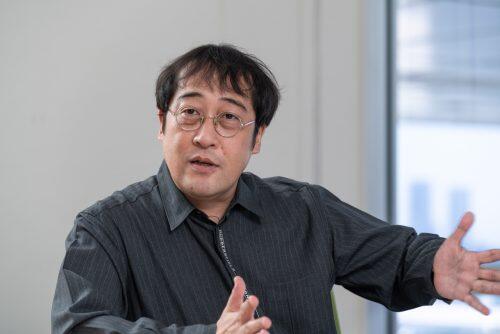
"マイナスの反転"や"違い"を面白がる
黒木
北風さんは、クライアントさんの商品を作るときに、生活者としての実感と商品がヒットするというところを、どう結びつけてゆかれるのですか?そこになにかロジックのようなものがあるのですか?
北風
"売れない理由"を真っ先に考えますね。売れないというか、ダメな理由、うまくいかない理由を、ものすごく暗いところから考えてみます。うまくいってないから弊社に仕事が来るわけですが、n=1(1人のサンプル)を考える前に、自分が冷徹な目で見てみると、うまくいかない理由が山のように見つかります。それを全部出し尽くすのが、最初にやることですね。「これでもか」というくらい悪いことを考えます。
私は人と人の関係でも、うまくいかないときには絶対に逃げないようにしています。「私はこの人のどこが嫌いでイライラしているんだろう」とずっと考えて、また会いに行ったりして。ネガティブな負のところに、実はすごくチャンスがあるんですよね。そこが変わるだけで、相手が喜んだり、私も楽しくなったり、いろんな転換が起きるじゃないですか。だからモノに関しても、売れない理由とか見向きもしてもらえない理由とか、あえてマイナスのところを見るようにしていますね。何が悪いかを徹底的に考えて、それを改善するやり方です。
黒木
僕らテレビ制作者でいうと、演者さんたちと付き合うときと同じかも。マイナスに思うことが反転したときはうれしいですよね。ダメなところが多い方がポテンシャルが高いこともあります。チームワークのことでいうと、ダメでドジなADさんほど実は大きく化ける可能性が高い。実際、"シュアな人たち"ばかりを揃えても、つまんないんです。中卒のADと東大のADが並んで会議にいても、同じ議題でもまったく違うことを思っているのでおもしろいんですよ。そこに化学反応もあるし。もともと日本語が苦手なんて奴もいるんですが(笑)。そういうADがいないとさみしい。仕事が出来ないとか、ダメだとかでそういうメンバーを外してしまうと、結果的にはチーム全体のパフォーマンスが落ちちゃうんですよね。
北風
同質性って危ういですよね。「似てきたな」と思うと、すごく危機感を感じます。ちょっとしっくり来ない人がいるとか、誰か一人怒っている人がいるチームとかのほうが健全だと思っているので。「違う=間違っている」と思う風潮があるけど、「違っている」と「間違っている」は別モノです。違っていていいし、違う部分を何かしらのおもしろみに変えたい。全部が自分の思ったようにいくと、逆に気持ち悪いですしね。そもそも自分が不完全なので、誰かに止めて欲しいというか、「違う」「おかしい」って言ってくれ!と思います。
黒木
日々ピンチを乗り越える作業を一緒にしていくなかで、仲間感やチーム感が生まれますよね。仲がいいとか気が合うとかよりは、戦友としての信頼関係があるかどうかが大事。バックグラウンドが違ってても、お互いにそういう感覚さえ持てればうれしいですよね。テレビだけでなく、きっといい職場ってそうなんだと思います。

互いがつながり、次なる構想へ
北風
番組をお金で買っているNetflixのようなメディアがあるなかで、番組づくりを含めて、今後どのようにテレビを盛り立てていきたいと思いますか?
黒木
世界を動かしているこの「スーパーグローバル資本主義」のシステムは当分変えられないし、資金力の大きいところが強いこともおそらくは変わらない。ずっと先の未来はわからないですけど。「費用対効果」という考え方が物事の最大の判断基準になってきているから、お金の力や同一性みたいな"安心感"に走ってしまう傾向が、思っている以上に相当強くなってきている気がします。これはバブル期以降の東京に30年住んでる実感として。
それを踏まえて考えると、逆にもう「チームワーク」とか「汗の量」とか「自分たちの物語」みたいなもので、細々と対抗していくしかないかなと思う部分もあります。世の中で圧倒的な「お金や効率の価値観」とはちょっと違うところの楽しみや喜びが少しでも出せたら、みんなにも共感して喜んでもらえるかなって。ウェブをはじめ色んな新しいメディアの方々とお話しするとみんな「マネタイズ」っておっしゃるけど、文化祭委員としては(笑)、マネタイズばかり言われてもあまりときめかない。このへんプロデューサーの発言としてはとても不適切ですが(笑)。「ちょっとそれとは違う自由もカッコよさもありますよ」みたいな余白が、テレビには存在しますし、それは絶対大事にしなきゃと思うんです。これはフジテレビのたくさんの先輩たちから教えられてきた多くのことの中で、唯一重要なことでして(笑)。テレビには何よりも自由とユーモアが一番大事なんだ、という価値観です。
だから北風さんが仰っていた「怖がらずに思い切ってバカなことでも言う」みたいなことが、より大事になってくるのかなと。たとえ世の中全体がAIの方向に行ったとしても、『ブレードランナー』のハリソン・フォードみたいな動き方をする後輩を、または中国SF『三体』の教授たちのような後輩を、どれだけ作れるか。それがいまの僕の使命だと思っています。
北風さんは何か次の構想などありますか?これまで取り組まれてきた、がんサバイバーのための企画とか、お父さんやお母さんの目線に立った企画とか、他にはないことだと思うのでとても面白いと思います。
北風
共働きが7~8割になってきているので、生活の知恵や時短術などをまとめてサイトにしているのですが、その知恵を結集した何かをやりたいですね。ディテールが大事です。私は「月に一度デパ地下惣菜だけをお弁当に詰めてラクをしましょう」というのを推奨しているんですが、たいていの人は彩りを気にしてプチトマトを加えようとしてしまいます。でも、そうしちゃうと、洗う、ヘタを取る、水気を取って入れるというプチではない手間がかかってしまうんです。月に一度ラクをする日にしたはずなのに、このプチトマト1個で台無しになるから「絶対にプチトマトは入れるな!」というディテールまで決め込んでいます(笑)。そういう細かい部分までの知恵が溜まってきているので、それらを一度まとめてみようかなと、仲間と一緒に考えているところです。
黒木
プチトマト! つい入れたくなりますよね!
北風
大人って子どもができると圧倒的に時間がなくなって、それでもママはネットワークがあるのでいろんな情報を入手できるのですが、イクメンのお父さんたちは情報入手も難しく、そういう声を発信する機会や余裕もありません。私は、子育て中のお父さんお母さんにビジネスの第一線で活躍してもらうためにも、できるだけ日中に簡潔に物事を決められるようにしたいと考えています。あとは、心や体の病気や、何らかの事情でうまくいかなかった経験がある人も、痛みがわかるがゆえの知恵や工夫、企画力があるので、積極的に仲間に入ってもらうようにしています。
黒木
世の中では「1回失敗したらもうダメだ」と判断されると思い込んじゃうことも多いけど、そんなことないですよね。北風さんのやってらっしゃるそういう会社としての姿勢を、世の中にもっと発信できるといいですよね。そういう企画も含めて、今後一緒に取り組めていけたらうれしいです。本日はありがとうございました。
北風
ぜひお願いします!本日はありがとうございました。
<了>
黒木 彰一(くろき しょういち)
フジテレビプロデューサー。1969年生まれ、京都府出身。1989年に上京し、1994年に早稲田大学政治経済学部を卒業後、フジテレビに入社。第二制作部(現、第二制作室。バラエティ番組制作)に配属。『夢がMORI MORI』でADデビュー。1998年深夜音楽番組『FACTORY』でディレクターに。2000年『BACK-UP!』で初演出。『SMAP×SMAP』、『笑っていいとも!』のディレクターを経て、両番組のプロデューサーに就任。『27時間テレビ 笑っていいとも!』『SMAP×27時間テレビ 武器はテレビ』など数々の番組でチーフプロデューサーを務める。2017年に配信音楽番組『PARK』、2018年に『アオハルTV』を立ち上げる。現在、第二制作室ゼネラルプロデューサー。民放連五輪プロジェクトチーム委員として『一緒にやろう2020』も展開中。
2019年10月現在の担当番組:『キスマイ超BUSAIKU⁉︎』、元旦特番『さんタク』『久保みねヒャダ こじらせライブ』、特番『天国が地獄』、特番『スモール3』など。
北風 祐子(きたかぜ ゆうこ)
電通 第1統合ソリューション局 チーフ・ソリューション・ディレクター。1970年生まれ、新宿育ち。1992年東京大学文学部社会心理学科卒業後、電通に入社。戦略プランナーとして新商品・サービス・店舗開発からコンテンツ開発、ブランディング、広告・販促キャンペーン企画まで一貫して携わる。2008年に「ママラボ」を創設、2012年~2015年にはキッズステーション番組審議委員・審議委員長を務めた。ママ・子ども関連でのコンサルティング実績は20年間に及び、共働き父母をサポートするサイト「時間がない.com」を運営中。
著書:『インターネットするママしないママ』(2001年/ソフトバンクパブリッシング)、『Lohas/book』(企画制作 2005年/木楽舎)









