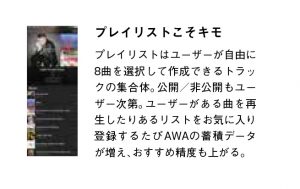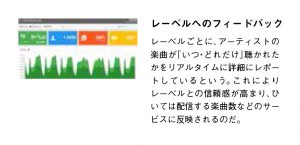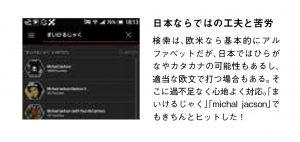リリースから5カ月あまりでアプリは580万ダウンロードを突破。2015年中には配信楽曲はおおよそ3,000万に届くという。国内最大級の定額制音楽配信サービス「AWA」。これを実現するために、サイバーエージェントとエイベックスが完全にゼロから、共同で新しい会社を立ち上げ、他の何者にも似ていないユニークな仕組みのサービスをつくりあげた。サイバーエージェント側の責任者・小野哲太郎さんに聞く、AWAという会社のつくり方。サービスのつくり方、そしてーー新しい音楽市場のつくり方。
※本記事は2015年12月に発売したSynapseに掲載したものです。
小野哲太郎
2007 年、サイバーエージェントに入社。社長室で藤田晋社長の運転手やアシスタントを経験した後、アメーバの著名人ブログのマネタイズに関わる。その後、藤田さん主導のVCに参画。1,000 人近くのベンチャー企業の経営者と接点を持つ。AWAではアプリ全般のものづくりを担当する。自身、大の配信サービス好き。映像、音楽問わずあらゆるサービスに加入し、ユーザーとしても楽しんでいる。
新しい会社をつくる。
サイバーエージェント藤田晋とエイベックス松浦勝人。
IT業界と音楽業界の風雲児2人はどんな風に新しい会社をつくったのか。
―AWAはどのように立ち上げられたんですか?
「日本の音楽ソフトの市場規模は、1998年には6000億円を超えていたのが、今や2000億円台。この5年ほどエイベックスの松浦(勝人)社長は対策を構想していたんです。日本の音楽市場の規模は世界2位なんですが、パッケージに限定すれば世界一。
でもCDで音楽を買う時代は終わりつつあって、サブスクリプション(=月額課金)を日本でもやってみたいと考えていたそうです。スウェーデンやイギリスでは、スポティファイ(世界最大の音楽配信サービス)の進出で音楽市場が下げ止まり上昇に転じたというデータがあります。違法な音楽配信が横行するなか、きちんとした配信を始めれば、正しく音楽が聴かれる土壌がつくれるのではないかと、松浦社長は社長の藤田(晋/サイバーエージェント)に、相談していました」
―それで、「やろう」と。
「はい。一緒に会社を50:50でつくろうということになりました。楽曲調達に関してはエイベックス側で行い、ものづくりに関してはサイバーエージェントで行うと」
―ちゃんと役割分担をして。
「はい。サイバーエージェントにとって単体で音楽業界で楽曲の許諾を得るのは未知の領域ですから」
―今、サイバーエージェントさんにお邪魔していますが、ここがAWAの事務所ですか?
「こっちはものづくりを行うプロダクトチームです。楽曲調達を行うエイベックスチームは、エイベックス本社内にいます。発足してからもオフィスはずっとバラバラなんです」
―そこは膝つき合わせてミーティングのようなことをされているんですか?
「ほぼ毎日行き来があります。プロダクトチームはひとつの部屋でエンジニアとデザイナーを中心に議論しながらものづくりをするというスタイルなんですが、エイベックスの場合は、例えばレーベルに話をする時に、先方と懇意にしている社員が別のマネジメントチームやイベント制作チームにいたりして、そうした社内のルートも使って交渉するので、AWAとして固まるよりもメリットがあるんです」
―小野さんはどういう経緯でAWAに入ったんですか?
「新卒で1年ほど藤田の運転手やアシスタントをした後、著名人ブログのマネタイズ部門の立ち上げを経て、AWAの直前は、1年半ほど社長室で外部ベンチャーへの投資を担当していました。でも、投資とか提携の仕事をやっているなかで、ものづくりに携わりたいという気持ちがあったので自分から手を挙げてやらせてくれと申し出たんです」
―当時の経験でAWAに生かせた点はありますか?
「多い日にはベンチャーの社長と5~6人に会うので、1年半で1000人ぐらいの方とお話しできて、それはすごくためになりましたね。特に、ものをつくる姿勢やチームビルドの考え方に関して。サイバーエージェントというひとつの会社のなかにいながら、多数の経営者の理念に触れて自社の良し悪しを客観的に知ることができたのは大きかったです」
新しいサービスをつくる。
ユーザーにどのように音楽に触れてもらい、リピーターになってもらうのか。
アプリ開発の意外すぎるスタートと独特すぎるリコメンドの仕組み。
―まず何から決めました?
「僕らのつくり方は特殊で、いきなりモックから。まず動きですね。曲送りをした時に、ディスプレイに曲がパラパラって見えて再生を押すとプレイヤーがバンって出てくる……その触った時の自然に気持ちいいなと思う体験づくりから始めました」
―その、動きの後は?
「機能ですね。モックをつくったのが7人。全員エンジニアですが、各々思い描く音楽サービスのモックをつくり始め、僕が機能案をつくりました。それでエンジニアから出揃ったモックと機能案とを照らし合わせていったんです。
そうすると”骨”みたいなものができる。横スクロールで5つのトップページが並ぶ構成。その上にスッとプレイリストが重なって出てくるルール。重なり方、戻り方の階層構造。ユーザーが感覚で操作する際に、矛盾があると”気持ち悪い”と感じるので、そこはひとつずつ潰していきました」
―今ケアしている点は?
「いかにユーザーに曲に出会ってもらえるか。世界中の数千万曲が聴けるなかから”聴きたい曲を選べ”って言われても分からない。実際AWAのユーザーの傾向を見ても、日々新しい曲に出会うか、昔好きだった曲に再会している人が継続してくれてるんですよ」
―具体的にどうリコメンするのでしょうか?
「いくつかのロジックを活用していますが、例えばそのひとつが『協調フィルタリング』。仮にAさんが①②③という曲が好きで、Bさんが②③④ならば、②と③が重なっているこの2人の嗜好は似ていると判断できます。するとAさんに④、Bさんに①を勧められる。もうひとついうと『曲と曲との相関傾向』に基づくロジックもあります。
波形やBPMや楽器の種類やボーカルの声質などを曲ごとに分析してデータ化し、似たデータの曲を勧めるもの。でも、曲単体を勧めるのではなくて」
―というと?
「最初こういう機械的アルゴリズムでお勧めしたら全然面白くなかったんです。例えば久保田利伸をよく聴いていて、勧められたのがスティーヴィー・ワンダーだとします。曲の波形も構成も似ているし、”アーティストシミラリティ”というアーティスト同士の相関関係的にも間違っていない。
でも勧められた側は”根拠がよく分からない”で終わりです。間違っていなそうだけどまさにこれをリコメンドして欲しかったとはバシッとはハマらない。そこで僕たちAWAが勧めるのは曲単位ではなく8曲から構成されたプレイリスト。どのプレイリストを選ぶかは『協調フィルタリング』と『相関傾向』によるもので、プレイリスト自体はそれぞれのユーザーが自分の感覚でつくったものです。
今、AWA上にはプレイリストが350万個あります。そこにはそれぞれ曲の説明が書かれているので、機械的に勧められるのとは、”耳の態度”が変わる。スティーヴィー・ワンダーがリコメンドされた時、久保田利伸がリスペクトしている人だと説明されていれば理由が分かって納得感が深まる。他にもいくつかの専門的な技術を使ったアルゴリズムによるリコメンドとプレイリストという人力のキュレーションの2段構えで、お勧めしています」
新しい音楽市場をつくる。
敏腕経営者2人の肝いりで生まれた新しい会社とサービス、だが、目指すところは自社の利益、というだけではない……。
―苦労されてる点は?
「大変なのは、ある程度できた後に問題を探して潰す作業。新機能ができた、デザインを当て込んでカッコ良くなった、動きを取り入れたらレスポンスが上がった……というのが一定基準まできた時に見直して、調整するところ。エンジニアで言うと、深夜1時までコードを書いて実装して動くようになった……という時に”5万行前のコードを直せば、再生ボタンの反応があと0.0001秒早くなるかも!”って思いついたとして、ごまかさずに”やり直すか!”って思えるチームづくり」
―そのレベルになると、つくり手の良心ですよね。
「実は考え方としては単純で、”このサービスを自分の子どもだと思えるかどうか”。”こうすればこの子がもっと賢くなる”って分かったら、親だったら絶対そうしますよね。そもそもAWAは自社の利益のためだけでなく、日本の音楽市場のV字回復を目指してるんです。レーベルの方にもそう説明して協力いただいてきました。シュリンクしている現実を受け止めつつ、音楽業界全体の未来を一緒に回復させたいと思っていると理解いただきたい、と」
―使命感を持てれば、自分ごと化しやすいわけですね。
「僕たちは、AWAが国民的な音楽サービスになることを目指しています。なので、サービスインの時点で”この層を取りにいく”という細かい想定はしなかったんです。ざっくりとしたアーリーアダプターの設定だけして、あとはその盛り上がりを気にして周囲の人が集まってくる図式になればいいなと。違法配信アプリとかYouTubeだけで音楽に接触している10代の人たちにお金を払ってもらえるようにしたくて」
―そのための課題は?
「本質的にはお金を払ってちゃんと音楽を聴いてもらう文化をつくらないといけないし、しかるべき収益がアーティストに届くことで、次のものづくりにつながって、更に音楽文化が繁栄していくというループに戻さないといけない。今は、音楽は無料だという概念が10代を中心に定着してしまっています。
時代の流れを強引に変えることはできませんが、時間をかけて今の時代に最適な手法で、かつアーティストが作品に対しての適切な評価に値する収益を上げる方法をつくっていかないといけない。だから今AWAにできることは会員数を増やすことです。従来のCDのビジネスモデルだと、基本、新譜しか売れなかった。
音楽好きの人は今後も新譜を買うでしょうし、ライブにも行くでしょう。それはそれでよしとして、僕らの今のやり方だと、リコメンデーションによってユーザーと旧譜を接触させ、それをマネタイズできる。今まったく動いていない旧譜に血を通わせて、そこからもお金が入ってくる……という積み上げをしたいんです」
―音楽配信は定着します?
「スポティファイが立ち上げたフリーミアムモデルは好調ですがこのモデルが正しいのかどうか、徐々にジャッジされるはずです。また新しいモデルが出るかもしれないし、僕らが提供できるかもしれない。今、音楽業界が生まれ変わるための種ができているので、できるかぎり大事に育てていきたいですね」
AWA とは
年内約3,000万曲の配信を予定。心地いい操作感でサクサク聴ける定額制音楽配信サービス。2015年5月スタート。利用開始より90日間は全機能無料。その後は全機能使えるStandardプラン(月額960円)や、一部機能が制限されたLiteプラン(月額360円)を選択可能。現在、スマホアプリに対応。11月下旬にはPC対応をリリース。http://awa.fm/